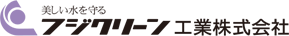社員のワークライフバランスを尊重し、
仕事と生活の両立を実現させるための
諸制度を構築しています。
 休暇制度
休暇制度
年間休日数
123日
有給休暇
最大20日/年 付与
※翌年度への繰り越し可能
 子育て支援
子育て支援
産前産後休暇
出産前6週間〜出産後8週間
育児休業
※最大子が2歳と3月31日まで延長可能、男性社員も取得可能
不妊治療休業
※最大1年
配偶者が出産する際の
慶弔休暇
最大3日
出産祝い金
50,000円支給
時短勤務制度
就業時間を6時間まで短縮可能
※小学校3年生の年度末まで
育児との両立の声
-
CASE01 海外事業部 K
-

-
経歴を教えて下さい
-
2013年に新卒でフジクリーンに入社し、以来、海外事業部で勤務しています。業務内容は営業事務・貿易事務を中心に、貿易関係の法令遵守のための調査や社内体制の構築に携わってきました。また、EPAなどの関税制度の調査・活用を通じて、企業の競争力向上とより円滑な貿易業務の推進に注力しています。
-
育休取得期間と取得理由を教えて下さい
-
第一子のときは1年半取得し、復職後数年勤務したのち、第二子では1年4か月取得しました。もともと結婚・出産後も働くイメージでいたことと、続けられる環境が整っていたため取得しました。
-
育休取得時のお仕事はどんな内容でしたか
-
第一子のときは部内の事務業務全般を担当し、貿易業務の進捗管理・書類保管のためのシステム構築も行っていました。第二子のときはオーストラリアとアジア向けの業務を担当し、法令遵守体制の構築の取り組みもこの時期に着手していました。
-
育休取得に向けて部内でどんな調整をしましたか
-
まず上司に相談し、育休期間や業務の引き継ぎについて話し合いました。第一子妊娠時はまだ部の人数が少なかったこともあり、新しく人員を募集して引継ぎしたため少し大変でした。第二子のときはメンバーも増え、国別に実務担当者がいる状態でした。国ごとにメイン・サブの2名体制にしていたため、サブの方に引継ぎ、業務理解も深かったので、スムーズに引継ぎすることができました。
また、普段からマニュアル等をしっかり作ったり、メールを業務に関わる人全員に共有したり、個人しか分からない業務があるという状態はなるべく避けるようにしていたのは良かったかなと思います。 -
育休中の過ごし方について教えて下さい
-
第二子のときは夫も1か月間の育休を取ってくれたので、余裕をもって赤ちゃんのお世話ができ、上の子の送迎なども担当してくれたのでとても助かりました。
外出できる月齢になってからは家族でたくさんお出かけしました。特に思い出に残っているのは、富士山の麓の音楽フェスへ行ったことで、私は野外フェスが初めてかつ子連れ参加だったため色々下調べしたり、簡易的なテントを購入したりしました。その後も、週末に地元の公園でテントを張ってのんびり過ごすのがとても幸せな時間でした。

-
育児と仕事の両立はどのようにされていますか
-
会社の制度としては時短勤務や時間休暇やテレワーク、家庭では時短家電と食材配達サービス等を活用し、家族の協力もあり何とか両立しています。時短勤務は法令上の会社の義務は子供が3歳までですが、当社は小3までできるのでかなり長期間の制度になっており、とても両立しやすい環境です。
気持ちの面では、部のメンバーの「お互いカバーしあう」という雰囲気や、上司の配慮にも大変助けられています。周囲への感謝の気持ちは忘れず、一方でもし自分が挑戦したい仕事があったら「育児中で時短だから仕方ない」と諦めずに手を挙げられるように、貪欲にやっていきたいと思っています。
-
-
CASE02 経営企画部 E
-

-
経歴を教えて下さい
-
私は2016年に新卒でフジクリーンに入社しました。最初は東京支店で大型浄化槽、産業廃水処理槽の営業を担当しました。2021年からは本社の経営企画部に異動し、会社全体の方針や経営計画策定に携わっています。
-
育休取得期間と取得理由を教えて下さい
-
私は、2024年10月下旬から2025年1月上旬までの約2ヶ月半、育児休業をいただきました。第二子となる娘が生まれたタイミングでの取得でした。4歳の長男もいて、育児と家事の両立はなかなか大変。妻と協力して家庭を支えるためにも、「今、この時期にしっかりと関わりたい」と思ったことが大きな理由です。また、部署のリーダーから「ぜひ育休を取って家族との時間を大切にして」と温かく背中を押してもらったことも、とても心強かったです。


-
育休取得時のお仕事はどんな内容でしたか
-
育休を取得した時期は、実は業務的にも大きなイベントが重なる時期でした。
10月末から年末にかけては、役員会や重点事業の進捗報告会、商品ラインナップ会議の運営、そして経営方針の策定など、複数の重要業務が同時期に集中していました。 -
育休取得に向けて部内でどんな調整をしましたか
-
私は小規模な部署に所属しており、育休前には部長や部下としっかり話し合いをしました。約1ヶ月間、進捗状況を共有しながら、スムーズに準備を進めることができました。
育休の初期は「出生時育児休業」を活用して、働く時間を少しずつ減らしながら、段階的に家庭中心の生活へとシフトしていきました。 -
育休中の過ごし方について教えて下さい
-
今回の育休は、「今度こそ家族としっかり向き合いたい」という気持ちを持って臨みました。というのも、第一子が生まれたときには、仕事の都合でなかなか育児や家事に十分な時間を割くことができず、後から「もっと関わってあげればよかったな」と後悔する気持ちがずっと心の中にありました。
だからこそ、第二子の誕生にあたってはできる限り家族のサポートをしたいと思い、育休の取得を決めました。
実際の毎日は、バタバタしながらもとても充実していて、息子や娘の小さな成長に気づけることが嬉しかったです。上の子の送迎や遊び相手になりながら、下の子のお世話をしたり、にぎやかで温かい時間が過ごせました。
特に料理が好きなこともあり、毎日の朝・昼・夜の食事を準備することが日課になっていました。
12月には家族が増えたことを機に、少し広めの家に引っ越し。新居での生活も、家族みんなで楽しみながらスタートすることができました。 -
育児と仕事の両立はどのようにされていますか
-
育休を経験して感じたのは、「家庭という安心の土台があるからこそ、仕事にも集中できる」ということです。
復職後も、できるだけ残業はせず、食事の後片付けや寝かしつけなど、家庭の時間を大切にしています。そのためには日中の時間を有効に使うことが必要で、スケジュール管理、仕事の効率化などを意識しています。
-
 健康
健康
インフルエンザ
予防接種
全額会社負担
乳がん、
子宮がん検査
全額会社負担
健康診断
二次検査
会社負担(上限あり)
健康相談窓口
外部の専門家に病気や看護、介護など様々な悩みを24時間相談できる。社員の家族も対象
治療と仕事の
両立時短制度
治療(不妊治療を含む)と仕事を両立する社員が時短勤務を選択できる。
 能力開発
能力開発
資格取得時受験
受験費用全額会社負担
(会社が承認したもの)
通信教育受講
全額会社負担
英会話レッスン
全額会社負担
 社外活動
社外活動
フジクラブ制度
健康の保持増進のためのスポーツ活動
リスキリングを目的とした文化的活動
ボランティア活動 など