| 藍は生きもの |
藍は建染(たてぞめ)染料といわれています。そのままでは水に溶けませんが、アルカリ性溶液の中では水溶性となり、繊維を染めることができるようになる染料のことです。しかも水溶性のままでは、一旦染めても、洗濯などで水につけると染料が溶け出してしまいます。ところが建染染料は、染めたものを空気中にさらすと酸素の働きで酸化して、再び水に溶けなくなるのです。
藍染を行うときすくもをそのまま水の中へつけても染液はつくれません。藍がめの中で醗酵させることにより、水溶性にしてやらなければならないのです。これを昔から藍を建てるといっています。
まず、木灰をかめに入れて灰汁を用意しておきます。すくもはあらかじめ湿らせて、粘りができるまで臼でつき、手でもみます。このすくもと灰汁に石灰を加えてかめに入れ、朝夕かきまぜていると、2〜3日で褐色の液になります。やがて液表面に無数の泡が浮いてきます。これは華とよばれています。つまり醗酵しているのです。こうした状態になったとき、はじめて布を染めることができるのです。一度建てた藍は、染める物の量にもよりますが1ヶ月〜3ヶ月くらいは染色が可能です。ただし、でんぷん室のものを加えてやらないと醗酵が止まり、染められなくなってしまいます。徳島では、でんぷん質のものとして、麦からつくったふすまを使うことが多いようです。
|

藍がめの中ですくもを発酵させるとやがて「藍の華」が浮かんできます。この状態になれば染色が可能です。
 |
染めたいものを藍がめの中へ入れます。染液の表面は空気にふれているため藍色をしていますが、中は茶色です。染液をよく浸み込ませたところでかめから引き上げます。引き上げた瞬間は茶色っぽい色をしていますが、またたく間に藍色へと変化していきます。
たとえば布を丸めて手で握ったり、あるいは棒に巻きつけたままこうした作業を行うと布全体には染液が浸み込みますが空気にふれていない部分もでてきます。そのまま水につけて洗うと、空気にふれなかった部分は全く色がつきません。
藍染めは、空気に触れる部分と触れない部分をつくり出すことにより、さまざまな模様を描き出すことができるのです。絞り染めも布の一部をつまんでくくったり、縫い締めることにより、空気に触れない部分をつくり出す染色技法です。ただし、藍がめに1度や2度つけただけでは、あまり濃い色は出ません。色を濃くするためには、藍がめにつけては引き出して空気にさらすという作業を、何度も何度も繰り返し行わなければならないのです。
|
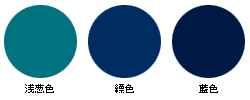 同じ藍染といっても、こうした染め方によって色調にかなりの違いが出てくるのです。当然、色調による呼び方も異なってきます。その中でも面白いのが「かめ覗(のぞき)」という色です。藍染の中でも一番薄い色とされ、白い布を、かめの中にちょっと覗かせた程度に染めた色とされています。もう少し濃くしたのが浅葱(あさぎ)、さらに縹(はなだ)、藍、紺といった具合になっていきます。このうち縹は濃淡によって深(さき)・中(なか)・次(つぎ)縹などに、さらに分かれます。 同じ藍染といっても、こうした染め方によって色調にかなりの違いが出てくるのです。当然、色調による呼び方も異なってきます。その中でも面白いのが「かめ覗(のぞき)」という色です。藍染の中でも一番薄い色とされ、白い布を、かめの中にちょっと覗かせた程度に染めた色とされています。もう少し濃くしたのが浅葱(あさぎ)、さらに縹(はなだ)、藍、紺といった具合になっていきます。このうち縹は濃淡によって深(さき)・中(なか)・次(つぎ)縹などに、さらに分かれます。
さて、紺と藍の違いですが、縹よりも濃くわずかに赤味をおびた深青色が紺とされています。吉野川は、その藍のふる里です。かつて染物屋を紺屋といっていたように、紺は染色の基本的な色でもあったようです。そして藍色というのは紺のように赤味を含まず、薄く黄味をかけた色を指していたようです。ただし、これらの色調の呼び方は時代によって若干の違いもあるようです。
|
とにかく、日本の染色の歴史の中で藍ほど多くの人に愛され、使われてきた色はありません。吉野川の上流に夕日が沈むとき、青かった空は徐々に青さを増し、刻一刻と色調を変化させていきます。あたかも藍がめから取り出されるたびに色を濃くしていく布のようです。藍色に染まった空の下を流れる吉野川。清きこの流れこそ、実は大自然をより美しく染める、清き染料なのかもしれません。
|

何百年もの昔から藍を育ててきた吉野川 |
